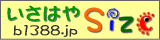《夫が先 経営者が先》十月のテーマ 経営者も家庭人
今週の倫理895号
男性経営者の皆さんは、奥様に呼ばれたら、
「ハイ」と元気な返事をしておられますか。
ご子息に呼ばれた場合も、同様に返答をしているでしょうか。
さらに、空返事ではなく、頼まれたことは即、実行に移していますか。
では、次のような場合はどう対応しているでしょう。
1 わが家の便所にトイレットペーパーの芯だけが置き去りにされていた。
2 玄関の靴がバラバラで、今にも靴が逃げ出しそうな状況に出くわした。
3 洗面所に娘が落とした髪の毛が散乱していた。
4 夕食後の台所に茶碗がそのままになっていた。
5 トイレや風呂が汚れていた。
6 家庭ゴミや資源ゴミが溜まっていた。
今週おすすめしたいのは、こうした場合、
家庭内において誰がやると決めるのでなく、
気づいた人が、気づいたことをさわやかに的確に処置するという実践です。
例えば、トイレットペーパーの芯が残っていたら捨てる。
靴は揃える。洗面所の髪の毛はティッシュで拭き取る。食器は洗う。
汚れているところは掃除する。ゴミは出す。
そして、心を曇らせることなく、
実行後は何事もなかったように朗らかに過ごすことです。
「誰が汚したんだ?」とか「なぜ誰もやらない」と、
犯人探しをしたり、責めたり、嫌々行なっては意味がありません。
もちろん、家庭内での約束事として役割を確認し合ったり、
躾として子供を教育することは必要です。
とはいえ、すぐに改善できない場合もあるでしょう。
その時は、自身の倫理実践のチャンスと捉え、果敢に挑み続けたいものです。
こうした取り組みは、即行の実践、
順序を正しく行なう実践と捉えることができるでしょう。
順序については次の通りです。
言うまでもなく、男女は同等であり、同権であり、平等な存在です。
相対した同士が合一することで生成発展(うみいだし)はなされます。
ここで大切なのが、順序(先後)を守るということです。
親である前に、先ず子である「子の倫理」をまもる。
父母の意見が異なる時には父に従う(父が先)。
親の子にして、後に妻の夫。
故に妻と親と意見の異なるときは、親に従う。
そして、妻の夫にして、子の親である。
(『丸山敏雄全集』八巻「夫の倫理」)
先が偉くて後が卑しいということはありません。
先後の秩序を守ることが幸福・発展の鍵であることを確認したいものです。
会社においては経営者が先、従業員が後です。
ということは、挨拶をするのも経営者が先ということになります。
これを先手の挨拶といい、経営者と社員の一体感を生む清き実践です。
夫婦においては夫が先、妻が後です。
ゆえに、挨拶をするのも夫からであり、
親愛の情に燃えてやさしくする夫の先んじた実践によって、
和やかな家庭は築かれていくのです。
今週は、男性目線で記しましたが、
女性の方もこれに準じて応用してください。
一般社団法人 倫理研究所法人局
今週の倫理895号
男性経営者の皆さんは、奥様に呼ばれたら、
「ハイ」と元気な返事をしておられますか。
ご子息に呼ばれた場合も、同様に返答をしているでしょうか。
さらに、空返事ではなく、頼まれたことは即、実行に移していますか。
では、次のような場合はどう対応しているでしょう。
1 わが家の便所にトイレットペーパーの芯だけが置き去りにされていた。
2 玄関の靴がバラバラで、今にも靴が逃げ出しそうな状況に出くわした。
3 洗面所に娘が落とした髪の毛が散乱していた。
4 夕食後の台所に茶碗がそのままになっていた。
5 トイレや風呂が汚れていた。
6 家庭ゴミや資源ゴミが溜まっていた。
今週おすすめしたいのは、こうした場合、
家庭内において誰がやると決めるのでなく、
気づいた人が、気づいたことをさわやかに的確に処置するという実践です。
例えば、トイレットペーパーの芯が残っていたら捨てる。
靴は揃える。洗面所の髪の毛はティッシュで拭き取る。食器は洗う。
汚れているところは掃除する。ゴミは出す。
そして、心を曇らせることなく、
実行後は何事もなかったように朗らかに過ごすことです。
「誰が汚したんだ?」とか「なぜ誰もやらない」と、
犯人探しをしたり、責めたり、嫌々行なっては意味がありません。
もちろん、家庭内での約束事として役割を確認し合ったり、
躾として子供を教育することは必要です。
とはいえ、すぐに改善できない場合もあるでしょう。
その時は、自身の倫理実践のチャンスと捉え、果敢に挑み続けたいものです。
こうした取り組みは、即行の実践、
順序を正しく行なう実践と捉えることができるでしょう。
順序については次の通りです。
言うまでもなく、男女は同等であり、同権であり、平等な存在です。
相対した同士が合一することで生成発展(うみいだし)はなされます。
ここで大切なのが、順序(先後)を守るということです。
親である前に、先ず子である「子の倫理」をまもる。
父母の意見が異なる時には父に従う(父が先)。
親の子にして、後に妻の夫。
故に妻と親と意見の異なるときは、親に従う。
そして、妻の夫にして、子の親である。
(『丸山敏雄全集』八巻「夫の倫理」)
先が偉くて後が卑しいということはありません。
先後の秩序を守ることが幸福・発展の鍵であることを確認したいものです。
会社においては経営者が先、従業員が後です。
ということは、挨拶をするのも経営者が先ということになります。
これを先手の挨拶といい、経営者と社員の一体感を生む清き実践です。
夫婦においては夫が先、妻が後です。
ゆえに、挨拶をするのも夫からであり、
親愛の情に燃えてやさしくする夫の先んじた実践によって、
和やかな家庭は築かれていくのです。
今週は、男性目線で記しましたが、
女性の方もこれに準じて応用してください。
一般社団法人 倫理研究所法人局